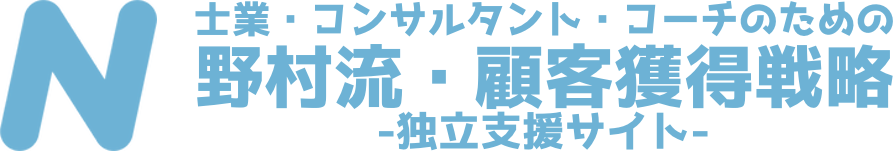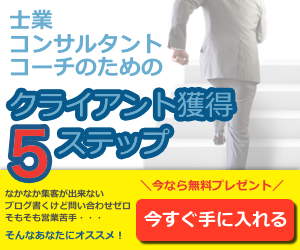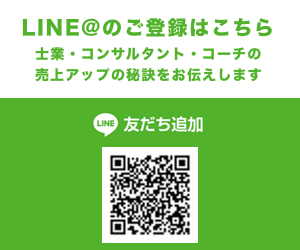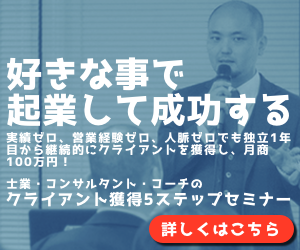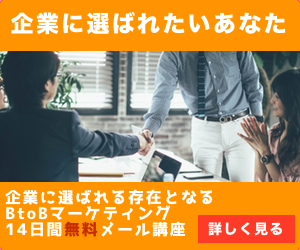中小企業診断士の野村昌平です。
今回は、多くの方が悩むであろう
「中小企業診断士、経営コンサルタントは専門性を打ち出した方がいいのか?」
という疑問について、私の経験に基づいた考えをお伝えします。
中小企業診断士の資格取得には、
組織論、マーケティング、財務会計など、
経営全般にわたる幅広い知識が求められます。
そのため、
「経営全般をサポートできるゼネラリストであるべきだ」
という考え方もあるでしょう。
経営全般のコンサルタント・ゼネラリストがよいのか?
専門分野のコンサルタント・スペシャリストがよいのか?
しかし、私がこれまでに多くのコンサルタントの
独立起業を支援してきた経験から言えることがあります。
目次
独立するなら「スペシャリスト」を目指すべき
結論から申し上げますと、
私は自分の強みを活かした専門性を打ち出すこと
を強くおすすめしています。
「私は経営コンサルタントです」という括りではなく、
「何のコンサルタントなのか」
「どんな分野の専門家なのか」を明確にすることが、
独立後の成功に直結します。
実際に専門性を打ち出しているコンサルタントは、
着実に売上を上げています。
なぜ専門性が必要なのでしょうか。
専門性を打ち出すべき理由
1.中小企業の戦略と同じ
中小企業診断士の試験で学ぶ戦略論にもあるように、
リソース(資源)の少ない中小企業は、
大企業と同じように「全方位戦略」をとるべきではありません。
「差別化戦略」や「集中戦略」で、
ニッチな市場を狙っていくべきだということは
理解できるかと思います。
そしてこの考え方は、
独立した中小企業診断士、経営コンサルタントにも当てはまります。
「私たち自身が自分の強みを活かし、差別化戦略や集中戦略を実行すること」
が、お客様に選ばれるための条件となります。
2. 「何でも屋」は選ばれにくい
業種に関わらず、これは共通の原則です。
例えば、飲食店で考えてみましょう。
「和食も洋食も中華も売っています」というお店より、
「うちの魚料理は絶品です」というお店の方が、
顧客は興味を持ちます。
コンサルタントも同じです。
「経営全般の悩みを何でも解決できます」
と言われても、経営者の方は
「結局、何を相談すればいいんだろう?」
と迷ってしまいます。
そうではなく、以下のように専門性を明確に打ち出すことが重要です。
- 「私はWebマーケティングが得意な経営コンサルタントです。Web集客なら任せてください」
- 「私は長年の金融機関勤務経験があり、資金調達や資金繰りが強みです。資金のお悩みなら私にご相談ください」
このように言われた方が、
悩みを抱える経営者は「この人に頼んでみよう」と思うはずです。
3. 紹介を生み出しやすくなる
専門性を打ち出すことは、直接の集客だけでなく、
紹介を生み出すためにも非常に重要です。
紹介者に
「経営全般の悩みを抱えている人がいたら紹介してください」
と依頼しても、相手は誰を紹介していいか迷ってしまいます。
しかし、
「IT導が得意なので、ITに悩む企業様がいらっしゃったらご紹介ください」
と具体的に伝えれば、
「だったらあの会社があるよ」というように、
紹介者もアクションを起こしやすくなります。
専門性を打ち出すための視点
専門性を打ち出す際は、以下の視点で絞り込むことができます。
- 業種で絞る:例)「飲食店専門」「医療機関専門」
- 業務で絞る:例)「資金調達専門」「組織人事専門」
- 業種と業務の両方で絞る:例)「飲食店専門の資金調達コンサルタント」
自分の強みや経験を棚卸しし、
「他者との違いを明確にする」ことです。
「私はこの分野、この業務、この業態の専門家なんですよ」
ということをしっかりと打ち出すことで、
数多くいる中小企業診断士や経営コンサルタントの中から、
クライアントに選ばれる存在になることができます。
ぜひご自身の強みと市場を照らし合わせ、
専門性を明確にして独立を成功させてください。