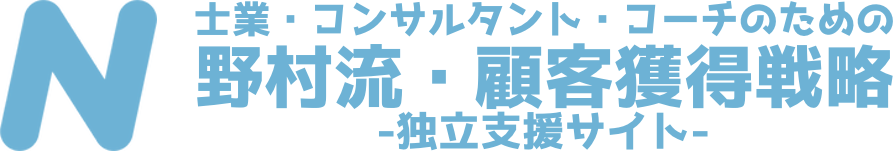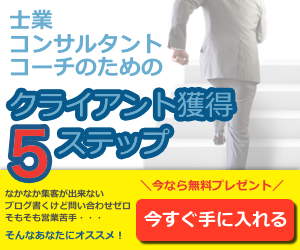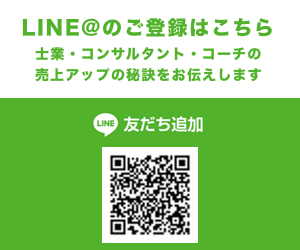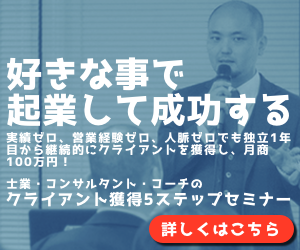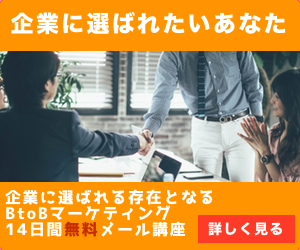中小企業診断士・経営コンサルタントとして独立して成功するには、
資格取得だけでは不十分です。
最も重要なのは、
安定的に仕事を得るための仕組みを構築することです。
今回は、中小企業診断士が顧客を獲得するための
3つの主要な方法について解説します。
目次
1. 協会や先輩からの紹介
独立初期の段階では協会や先輩の中小企業診断士からの紹介は、
仕事を獲得する上で非常に有効な手段となります。
メリット
- 仕事の獲得が比較的容易:
特に経験が浅い段階では、紹介を通じて案件を得やすいです。 - 実践的な経験の蓄積:
先輩の指導を受けながら実務経験を積むことができ、自身のスキルアップに繋がります。
デメリット
- 案件単価が低い傾向:
紹介案件は、単価が低めに設定されているケースが多いです。 - 下請け的立場になりがち:
紹介元との関係上、自身の裁量が制限され、
下請けのような立場での業務が多くなる可能性があります。
2. 公的機関や金融機関からの紹介
商工会議所のような公的機関や信用金庫などの金融機関も、
中小企業診断士の重要な顧客獲得チャネルとなります。
これらの機関では、専門家登録制度などを通じて、
中小企業へのコンサルティング案件を紹介してもらうことが可能です。
メリット
- 信頼性の高い案件:
公的機関や金融機関からの紹介は、企業からの信頼を得やすいのが特徴です。 - 契約への足がかり:
企業にとっては費用負担が少ない(あるいはゼロの)専門家派遣制度を利用できるため、気軽に相談につながり、その後の本格的な契約へのきっかけとなることがあります。
デメリット・注意点
- 案件単価は低め:
紹介案件と同様に、単価は高くない傾向にあります。 - 「お試し」と捉える視点:
あくまで本契約へ繋げるための一歩と捉え、自身の専門性をアピールする機会として活用することが重要です。 - 積極的なアピールが必要:
登録すれば自動的に仕事が舞い込むわけではなく、自身の得意分野などを機関に積極的にアピールする必要があります。
3. 自分で仕事を生み出す仕組み作り
これが、中小企業診断士として長期的に成功し、
高単価の案件を獲得するために最も重要な方法です。
メリット
- 単価設定の自由度が高い:
自身の提供する価値に見合った適正な単価を設定できます。 - ビジネスの安定性:
紹介に依存しないため、特定の紹介ルートが途絶えてもビジネスを継続できる強固な基盤を築けます。 - 事業の成長:
自身の戦略に基づいて能動的に顧客を獲得できるため、事業拡大に繋がりやすいです。
具体的な方法
- セミナーの開催: 自身の専門分野に関するセミナーを開催し、見込み顧客との接点を作り、信頼関係を構築します。
- 情報発信: ブログ、SNS、YouTubeなどを通じて専門知識やノウハウを発信し、自身の専門家としてのブランディングを行います。
- 既存案件からの派生: 紹介案件や公的機関からの派遣案件をきっかけに、顧客との信頼を深め、より高単価な本契約へと繋げる営業活動を行います。
まとめ
中小企業診断士として独立後、
安定的に年収1,000万円以上を目指すのであれば、
最初は紹介案件で経験を積むという考え方もあります。
しかし、最終的には
「自分で仕事を生み出し、獲得する仕組み」を構築することが不可欠です。
これにより、単価を適切に設定し、
自身のビジネスを力強く成長させることが可能になります。